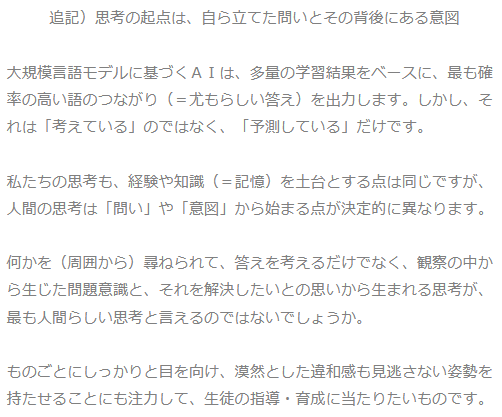
ひと月ほど前のこと、7月25日(金)の朝日新聞『折々のことば』に美術家・評論家である岡﨑乾二郎氏の「批評の始まりは、まず説明しがたい奇妙な細部を見つけることだ」との言葉が紹介されていました。
どんな絵にもうまく説明できない細部がある。そこで感じた違和を抑え込み、既存の枠組みで説明しようとすると、対象は歪(ゆが)んでしまう。逆にその違和をもはや違和としない理解の枠組みを組み立てるのが批評だと、造形作家・評論家は言う。これは科学上の発見や医師の診断にもいえることだろう。山本貴光によるインタビュー「批評の仕組み」(「美術手帖」7月号)から。
岡﨑氏の云う「特異点を見つけ、それを説明し得る仮説を立て、理解を深める作業」には、科学上の発見にも通底するものがあるとの指摘。
ふとしたことで抱いた「違和感」をスルーしないことが、物事の構造や意味を明らかにしていく出発点になるのは間違いないところでしょう。より良い社会を作るためにも、日々の中に感じる「違和感」に正面から向き合い、正体を捉えることの大切さを、改めて感じさせられました。
これまでに起こしたブログ記事にも、同じような意識に根差したものが幾つかありました。この意識に立ち、指導を計画し、授業をデザインしていくことは、PISAが測ろうとしている「創造的思考力」を育むところにも繋がっていくのではないかと思います。
21世紀型能力の中核をなす「思考力」の構成要素の一つに「問題発見力」がありますが、問題を見つけるには、まずは「対象をじっくり/精緻に観察」することが不可欠。グラフやデータは言うまでもなく、写真や動画、絵画や図版、文章で書かれた資料なども「観察」の対象です。生徒にこうした対象を観察させる機会は十分でしょうか。「問い掛け」と「気づきの交換」を配列したトレーニングの場を作りましょう。
- 問題は「観察」したものの中に見つかる
- 観察の力を養う「問い掛け」と「気づきの交換」
- 観察のための「データ加工」の方法も学ばせていく
- 言葉にする/手で書くことで、観察はより精緻に
より良い未来を築くには、単なる知識の蓄積だけでは不十分。「社会を変えるのは、答えを知っている人ではなく問いを立てられる人」です。より良い社会に近づけるために解決すべき問題は、頭で考えているだけで自然に湧き上がってくるものではありません。身の回りのことや見聞きしたことに注意を向けて、何らかの疑問を抱くところから、さらに思考を重ねる中で、解を導くべき問いが具体化していきます。
- 最初のフェイズは、観察した中に疑問を抱くこと
- 論理的・批判的に考える機会をしっかり整える
- 解決策の創造やアイデアのブラッシュアップにも問い
生徒に限りませんが、昨今、よく耳にするのは「褒められて伸びるタイプ」と自称する声。わからなくもありませんが、他人に褒めてもらわずとも伸びる人はいるし、褒めてもらえないからと簡単にやる気を失うようでは、少々「生きる力」に欠けるかも。自ら目標を設定し、その達成への道程を描き、実行できるように導いてこそ、自己効力感を備え、他者評価に依存しない、タフでブレない生き方を生徒は身につけます。
- 自分を客体化し、進捗と改善課題を捉えることで
- 目標設定は、進捗を可視化するための「物差し」
- 成果のたな卸しをしながら、次の作戦を考える
- 叱責や批評も前向きにとらえる「自律的な視点」
- 正しい目標設定に必要なのは十分な「自己理解」
探究活動の評価は、成果物の完成度や新規性に観点が偏りがち。プロセス全体に注目し、生徒がどんな能力やスキルを獲得したかを評価の中心に据えるべきと考えます。正しくプロセスを踏んだ探究活動なら、最初に立てた問いは、調べたり、考えたり、フィードバックを受けたりする中で、新たな形を得てバージョンアップしていくはず。探究の過程が進む中で、問いがどれだけ深化したかに着目し、活動を評価しましょう。
- 問いの深化は、探究が進んだことを示す指標
- 問いを立てる=解決すべき課題の設定
- 探究の過程を踏む中での問いのバージョンアップ
身の回りに起きている問題の多くは、日々の授業や探究活動の中に、学び、解決策を考える機会を持ち得るもの。各単元の学習ので扱えるものもあれば、単元を跨いだ融合問題を設定することで学習機会が作れるものもありますし、他の教科と連携した合教科型学習で扱うべきものもあります。そうした問題について学ぶ中で、生徒は「問題発見・解決力」や「持続可能な社会への責任」「社会参画力」を獲得していきます。
- 教科書の記述に別の視点を与えて学ばせてみる
- 複数の問いを与えることで、様々な切り口を持たせる
- 調べ学習では、サブテーマを設けて割り当てる
- 体験学習は、多角的な学びの絶好の機会
拙稿「記憶は思考(理解や予測)の大事な道具」の追記で書いたことには、本稿にまとめた記事群とも通底するものがあるように感じます。
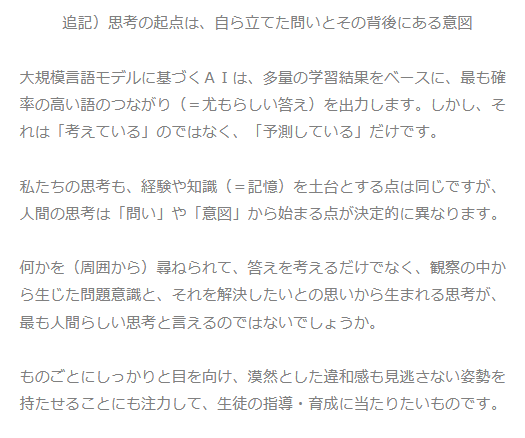
教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一
