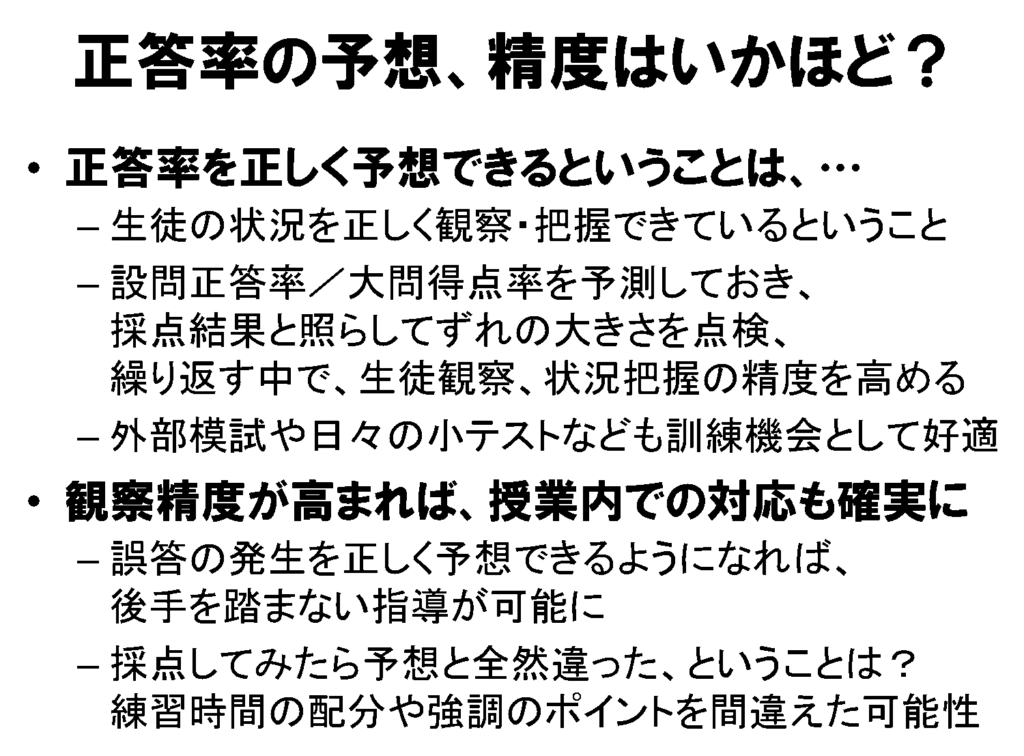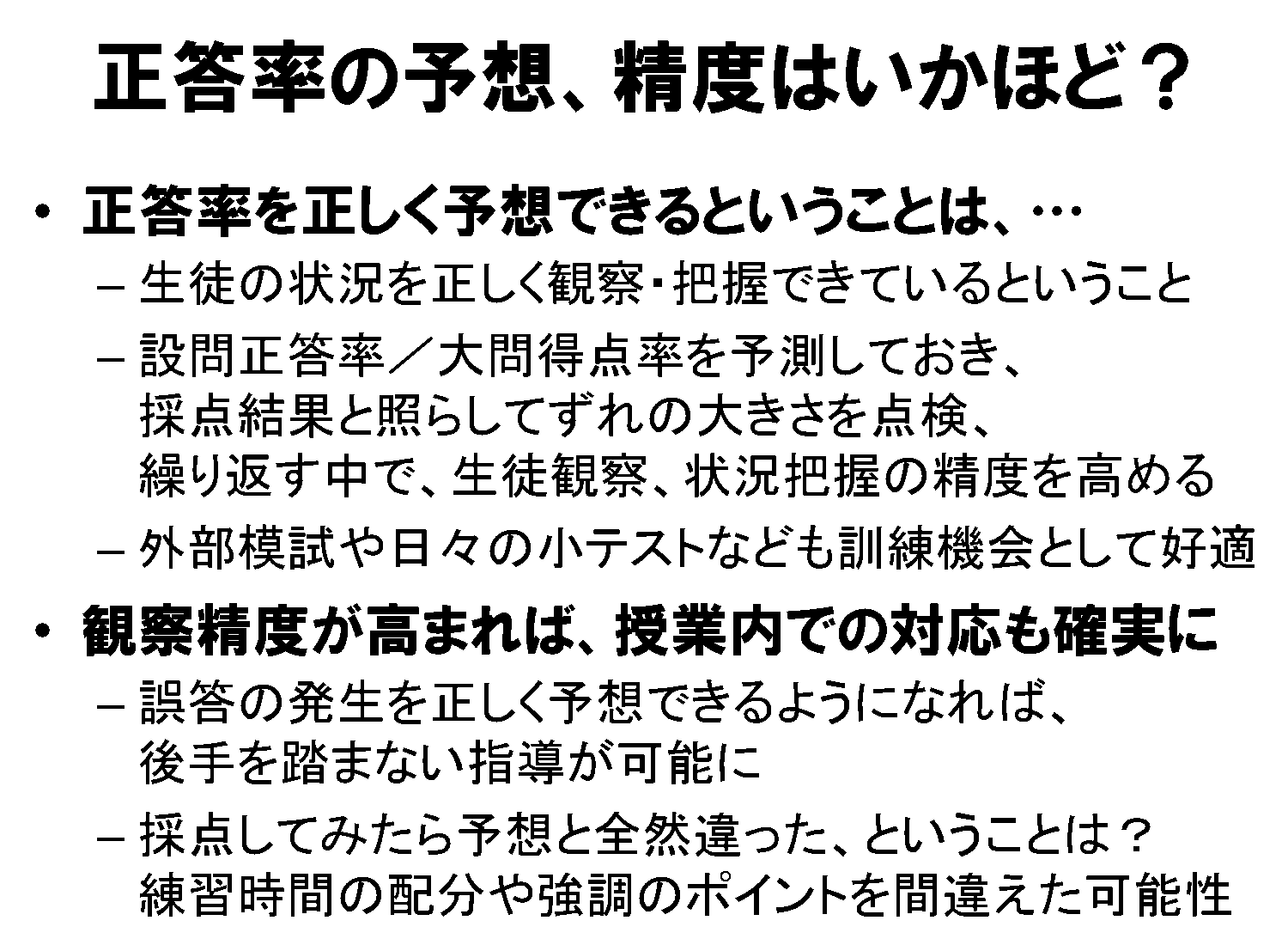
正答率を正しく予想できるということは、問題が要求する様々な学力に照らした「生徒の状況把握」が正確に行えているということです。
教科学習指導は、目標学力と生徒の現況学力との差を埋めるための行為であり、正答率の予測精度(=現況学力を正しく把握しているか)は、指導設計の妥当性に大きく影響を与えます。
様々な場面で実際に予測を行ってみて、ご自身の予測力を常に点検するとともに、精度の向上を図る努力も怠らないようにしたいものです。
2016/09/09 公開の記事をアップデートしました。
❏ まずは模試を使って、ご自身の正答率予測力を点検
正答率の予測力を確かめるには、公開模試が好適な材料のひとつです。
模試なら業者が大問別の得点分布やクラス別平均点などのデータも揃えて来てくれるでしょうから、改めて解答情報(正誤など)を集めたり、集計を取ったりといった手間が省けます。
模擬試験の資材が到着したら実施前に問題に目を通すと思いますが、その中に見つけた「良問」については、ご自身が担当するクラスの生徒の顔を思い浮かべつつ、その問題の正答率を予測してみましょう。
ここでの目的は、設問ごとの正答率の予測を行い、その精度を高めていくことですから、全問を対象に総合点を予想する必要はありません。
ある大問での予想が上振れし、他の大問での予想が逆に振れて、双方のハズレが相殺されて「結果オーライ」(総合点の予想はほぼ当たり)というのでは、正しく正答率を予測できたことにはなりません。
正答率予測の対象にするのは、思考や表現の要素を多く含む問題を中心に選びましょう。
知識の有無をダイレクトに試すタイプの問題では、直前に復習をした/ヤマが当たったといった、本来の学力とは関係が希薄な要素が正答率を左右しますし、解析で得られる指導改善へのヒントもわずかです。
蛇足ながら、総合点は各大問の得点の積み上げに加えて、全体の問題量や手間のかかる問題が何問目に配置されているかなどでも微妙に影響を受けますので、予想はなかなか大変です。
❏ 問題が求める要素ごとに生徒の充足度を予想
正答率を正しく予想するといっても、大学入学共通テストなどの平均点予想と違い、予想が当たればそれでOK/目的を達したというわけではありません。目的とするところは、授業改善の前提たる「現況学力の正しい把握」の実現にあります。
個々の設問が要求する、知識・理解の有無、手順への習熟、解法立案の発想といった要素に分けてみて、教えている生徒がそれぞれをどれだけ満たしているか、定着度/習熟度を予想してみてはじめて、タイトルにある「授業設計の最適化」に繋がる知見が得られます。
「この部分は、ほぼ全員がクリアできているはず」
「ここは、いいところ上位の3分の1くらいかな」
…といった具合に見立てを重ねた結果が「予想した正答率/得点」ですので、それが大きく外れていたということは、生徒の学力を正しく把握できていなかったということになるはずです。
デジタル採点が普及して、個々の生徒がどの答えを選んだか/どう答えたかまで確認できるようになれば、「再現答案を生徒に作らせ、手入力でデータ化して」といった負担を抱えずに、指導者としての見立ての正しさを更に詳細に点検できますが、実現はもう少し先でしょうか。
❏ 正答率の高低に加え、予想を上下どちらに外したか
正答率が十分に高かったら、その問題を解くのに必要な要素はそれまでの指導で十分に養えていたということ。逆に正答率が低い場合、どんな学習活動を授業内に配列すれば良かったか考えるのは当然です。
焦点を当てるべきは、予測した正答率と実際が一致しているかどうか。
予想が上に外れた(実際より高い正答率を予測した)場合、「わかっているはず」との思い込みで指導をしていたのかもしれません。
予想を下に外したなら、既に生徒がわかっているところを無駄に重ね塗りしたのかも。生徒に自力で取り組ませれば良いところに、貴重な授業時間を割いたかもしれず、学習活動の配列を見直すべきでしょう。
いずれの場合も、生徒の学力を正しく見極めることができていなかったということであり、授業での目標設定や主眼の置き方にも修正すべきところがあったと考えられます。
模試の大問ごとの平均点予想や、得点帯別の人数の予測には、教科の先生方で集まってワイワイやってみるのも良いかもしれません。予測精度の高い先生が普段の授業でどんな観察を心がけているかをその場で伝えてもらえれば、貴重なヒントも得られそうです。
折しも、初めての「大学入学共通テスト」が実施されました。自己採点結果も集まりました。生徒の顔を思い浮かべつつ、自校の生徒/担当しているクラスの生徒の得点分布が正しく予想できていたか点検してみると、次年度の指導に生かせる様々な気づきが得られるはずです。
❏ 思考のプロセスの一つひとつに観察の目を
思考力、判断力、表現力を試すことに主眼を置いた問題は、知識の有無を試すだけの問題(お決まりの「頻出問題」も、解法を覚えていれば正解を導けるという意味で、ある種の「知識問題」です)と比べて、正答率の予測がはるかに難しいのは経験的にもお分かりだと思います。
こうした問題に答えを導くまでの過程には、問題文を読んで題意を汲み取り、見通しをもって解法を立案し、答えの構成を考える、などなど、実に様々かつ複雑な「思考のモジュール」が組み込まれています。
個々のモジュールを意識していないと(=問題をざっくりと感覚で捉えているだけだと)、初めて取り組ませる問題に対し、個々の生徒がどのような頭の使い方ができるか、予想が立たず、正答率/得点率の予測精度もどこかで頭打ちになります。
日々の授業でプロセスに焦点を当てた問いを十分に駆使することや、生徒の思考過程を覗き込むための「観察の窓」を開く(活動させるのは観察のため)ことが、思考力や判断力を求める問題での正答率予測の精度を高め、ひいては授業設計の最適化を図る土台を作ってくれます。
当然ながら、ここでの目的にマッチした観察の機会を確保するには、少なくとも以下の2点は常に意識の上位に置くべきであると考えます。
1. 授業の中で問い掛けを絶やさないこと
→ 問い掛けの多い授業が良い授業
2. 新しい学力観に沿った適切な問いを用意すること
教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一