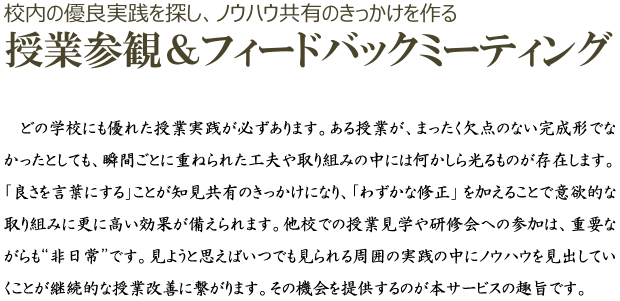
ある高校を訪ねて行った「授業クリニック」で見つけた、様々な場面で活用できそうな指導の手法を幾つかピックアップしてご紹介します。
どの学校でも授業公開や相互参観が行われていると思いますが、複数の先生方が同じ授業を見て、それぞれの気づきを言語化してシェアするところまで、取り組みを進められば、効果はさらに大きくなります。
もちろん、授業の中にさらなる工夫が必要な部分(改善課題)を見つけることもありますが、その解決法を考えるにも、先生方がそれぞれの見立てや意見を持ち寄った方が、より良い答えが見つかるはずです。
さて、それではクリニックの対象となった授業からの学びです。たくさん優れた点に加えて、少しの発想転換で大きく改善が図れそうな場面がいくつも見つかりました。その場にいたつもりでお読みください。
❏ 問いを重ねて進めるスタイル
ある先生の授業では、「問いを重ねて進めるスタイル」が、生徒の反応と集中を非常によく引き出していました。
問いを投げかけ、少し時間を与え(長すぎないことが、集中力を維持させるのに大切)、机間指導で状態を把握した上で発言させていました。
もし、状況把握なしに出席番号などで指名していたら、あらぬ発言が返ってきたり、生徒が押し黙ってしまったりして、スムーズな展開が損なわれていたはずです。
- 生徒を指名して発言させるとき(全3編)
また、問いで引き出した一人の発言を起点に、次の問いを重ねていくスタイルは、先生が予め考えておいた授業案にただ沿って進められる、ある種の予定調和的な流れと違う、ライブ感も醸していました。
問いを介在したインタラクションが実現していた教室だと言えます。
❏ 板書を使った、問いとのその土台の共有
さらに、生徒の発言は、多少の間違いや不足を含んでいても、そのまま黒板に書き出しておられました。
やり取りを繰り返しながら、模範解答ができあがるまで板書しないのでは、何をやっているのかわからなくなる生徒も現れますし、やることがなくて退屈し出す生徒も出てきます。
未完の回答でも、それを板書することで、他の生徒にも「今、やろうとしていること、これから考えなければならないこと」が視覚を通じて無理なく共有されます。
口頭で伝えただけのときとはまったく違うレベルで、教室内の意識を揃えることができます。
黒板に書き出した生徒の発言に、本文からそのまま写しただけで意味が押さえられていない言葉(ちなみにこの授業は国語です)が含まれていたら、辞書で調べさせて脇に別色のチョークで添えるかたちで「開いた言葉」に書き換えて見せていました。
生徒の答えをもとに正解に近づけていくというアプローチです。教員が作った答えから逆算的に教材に関わるのとは全く違った学びが作り出されていたように感じます。
❏ 様々な形で音読を重ね、相互にチェック
また、別の先生(こちらも国語[古典])の授業では、多彩なバリエーションで生徒に音読を重ねさせていました。その中で生徒が、文の構造と内容を理解していく様子がとても印象的でした。
構造などについての説明にまとまった時間を欠けるわけでもなく、生徒は集中して音読を重ねているだけですが、まさに「読書百遍義自ずから見る」を字で行くような場面。そうした効果を身をもって体験しているからこそ、音読という活動にも身が入るのだろうと思いました。
また、正しい読みができているかを互いにチェックする場面もありましたが、チェックという作業を通して音読の細かなところまで注意を向けることも、構造などの理解に奏功しているようにも見受けられます。
そもそも、互いにチェックし合う以上、ぼそぼそと不正確な音でごまかすこともできません。音読で声がでないような教室では、ペアでのチェックというタスクを与えることは有効だと感じました。
後編に続く
教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一
